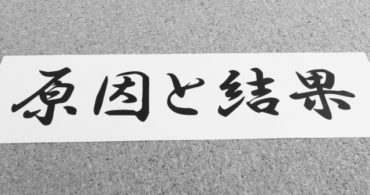- 現代文
- 2016-2-17
文系科目のわからない問題に挑む!【分割と視点】

文系科目でわからない問題にあたったとき、あなたはどうしますか? ここでは、分割と視点というワードに着目して紹介します。文系科目がわからないという受験生は必見です!
分割して検討する!
 わからない計算問題にあたったときの対処法としては「分析する」ことが有効ですが、同様に文系科目でも有効です。とくに、センター試験の国語などの選択肢が長い問題にあたったときには、「部分に分けて検討する」という方法が有効です。
わからない計算問題にあたったときの対処法としては「分析する」ことが有効ですが、同様に文系科目でも有効です。とくに、センター試験の国語などの選択肢が長い問題にあたったときには、「部分に分けて検討する」という方法が有効です。
文系科目の長い選択肢全体を間違いなく把握することができればよいのですが、全ての問題でそれができるかというとなかなか難しいです。そして、選択肢全体を雰囲気で捉えてなんとなく選んでしまうと、まんまと出題者のワナに引っ掛かってしまいます。文系科目の問題がわからないという受験生が陥ってしまうのはここです。ここで「部分に分けて検討する」という分析ができる受験生は、選択肢に仕掛けられた出題者のワナに引っ掛かることなく正答を選ぶことができるのです。
部分に分けて検討するためには、まず選択肢をいくつかの「まとまり」に分割します。そして、分割したそれぞれの「まとまり」が本文や設問の条件とつじつまが合っているか、一つ一つ確認していきます。選択肢全体としてなんとなく合っていそうでも、一部でもつじつまが合っていなければそれは正答ではありません。このプロセスによって、なんとなくではなく、確信を持って選択肢を選ぶことができます。文系科目の問題がわからないという受験生こそ、まとまりに分割していくことで一つ一つをシンプルに考えることが重要なんです。
また、「まとまり」のなかに強い限定がある場合には、そこに注目する必要があります。たとえば、「絶対」「必ず」「~はすべて」「~しかない」などです。これらの言葉が含まれている選択肢は誤りである可能性が高いと言えます。同様に、英語でも「all」「never」といった単語を使っている選択肢には注意が必要ですね。
それぞれの視点から考える!
 複数の立場や考えが存在するようなテーマは、その立場や考えが多くなるほど複雑化して難しくなります。たとえば、現代文における小説、日本史、世界史における複数の国家間の関係に関する問題、古文における複数の登場人物が出てくる文章などがあります。
複数の立場や考えが存在するようなテーマは、その立場や考えが多くなるほど複雑化して難しくなります。たとえば、現代文における小説、日本史、世界史における複数の国家間の関係に関する問題、古文における複数の登場人物が出てくる文章などがあります。
これらの問題を考えるとき、自身の意見を持ったり、登場人物の気持ちに共感できることは素晴らしいのですが、その前提として客観的に事象を把握する必要があります。
一方の立場や考えでは正しいと思える内容でも、他方の立場や考えでは誤りだとされることも多々あります。客観的に事象を把握して、それぞれの視点から考えるように意識しておかないと、問題の全体像をとらえることはできません。そして、問題の一部しか把握できていないと、他の問題で立場や考えが変わった途端に分からなくなってしまい、安定して得点することは難しいです。
それぞれの視点から考えることを習慣化し、しっかりと問題の全体像をとらえることができるように練習しておきましょう!文系科目の問題がわからないという意識を持っている受験生は特に注意してみてください。一つ一つの立場とその立場の考えを整理すれば一つ一つがシンプルに考えられ、文系わからないという意識はなくなるはずです!
大学受験勉強法メディア編集部
具体的には、実際に効果があった勉強法や、受験生のためになる受験に関するお役立ち情報を発信していきます。
大学受験勉強は勉強法が命です。合格を勝ち取る受験生は、結果が出る勉強法で勉強しています。
どれだけいい予備校に通っても、いい参考書を使っても、時間ばかりかかって身に付かない勉強法でやっていては、いつまでたっても結果は出ません。
今すぐ正しい勉強法を身につけて、志望校合格を勝ち取りましょう!
最新記事 by 大学受験勉強法メディア編集部 (全て見る)
- あなたは解ける?大学受験勉強を始める前の実力チェック - 2017年7月15日
- 【必読】最速で英単語を暗記!英単語の覚え方! - 2017年5月26日
- 科目別勉強法概要④理科・社会 - 2016年11月17日